



チームのJ2降格、募金活動の停滞といった試練を、設計施工者に決まった竹中工務店もまた、固唾を飲んで見守っていたという。10年5月に行われたプロポーザル形式(提案競技)でのコンペから約2年。竹中としては、32,000人から40,000人への収容人数の変更や11年3月に発生した東日本大震災による資材高騰も受けて、コンペ時のデザインをもとに細部の調整を続けてきた中で、12年末には基本設計がほぼまとまっていたからだろう。12年末に直面したJ2降格というまさかの事態に「このままでは工事を続けられないのではないか」と危機感を抱いたと聞く。竹中のコンペ設計チームにおいて、設計マネージャーとしてコンペ時に統括の役割を担い、竹中を代表してプレゼンテーションを行った川合智明が振り返る。
「設計施工者に決定して以降は『募金で作るスタジアム』という新たなスキームに賛同し、『日本に誇れるスタジアムを作ろう』を合言葉に準備を続けてまいりました。募金で作るということは、すなわち、募金をしていただいた皆さんが発注者ですからね。皆さんの想いを裏切らずに、多くの方々の共感を得られるスタジアムを建てられるか、ということに大きな責任も感じていました。ただ、今回は募金活動と建設が並行して行われるという異例の流れで工事が進むことになっていたため、弊社といたしましては本当に募金が集まるのかということに不安を覚えていたのも事実です。ガンバさんからは都度、募金状況をご報告いただいていましたが、ガンバさんにとってもJ2降格は、クラブ史上初めて直面する出来事でしたから。それがスタジアム建設や募金活動にどのような影響を及ぼすのか、我々としても非常に心配しておりました(川合)」
実際、設計チームで当初からリーダーを務め、川合の後を引き継いだ大平滋彦も、J2降格が決まった直後に募金団体に足を運んだ際のやり取りを、鮮明に覚えているという。
「心苦しさはありながらも、正直に『今のままの募金状況では躯体工事までしかできず、屋根や観客席の椅子、多くの設備工事ができなくなってしまいます』とお伝えしたら、金森理事長が重い口を開かれて『大平さん、屋根や座席がなく、ピッチだけがあって何ができるのでしょうか?』と尋ねられたんです。それに対して私は『練習はできます』とお答えするしかありませんでした。結果的に、会議室に漂う重い空気を感じながら、その時は『お互いに、ここから何ができるのかを考えましょう』と別れたのですが、私自身はその時点で今回のお話が頓挫することも覚悟していました。そしたら、2日後だったか、金森さんから連絡をいただき『必ず新スタジアムを実現させたい。計画をもう一度見直してほしい』と言われたんです。その決意に触れて我々も構造担当や設備担当を含めた全員が再度集まって、できる限りコンパクトで合理的な計画案となるように使用する資材を1ミリでも少なく、それによって1円でも安く建てられる方法を細部の細部まで見直しました(大平)」
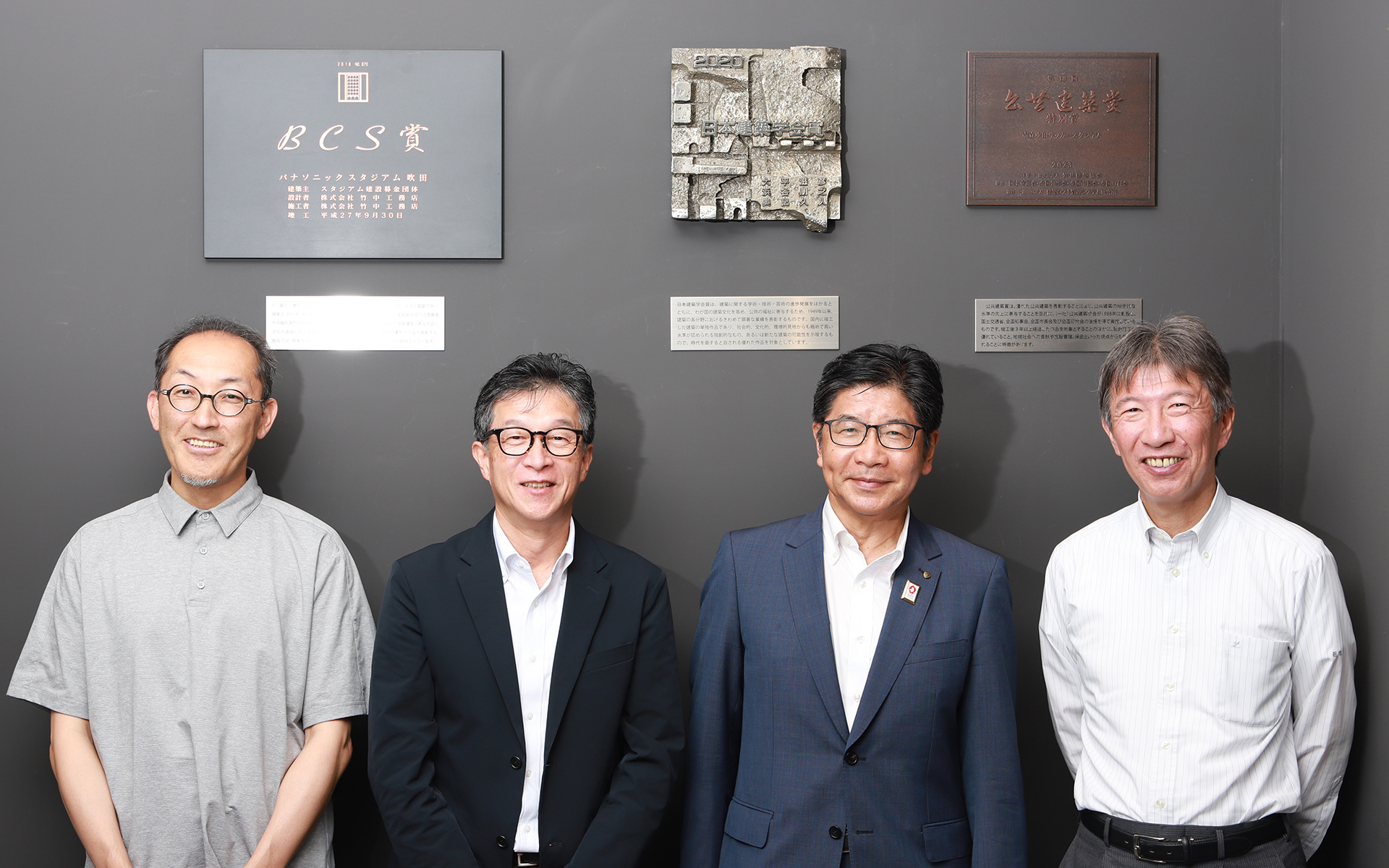
結果的に、仮に募金が140億円に到達せず、工事費を見直さなければいけなくなった場合は『40,000人収容』はそのままに、スタンドの屋根や大型ビジョンにかける費用などを削減することも視野に入れながら工事を進めることで合意し、再び新スタジアム建設に向けて動き出したという。
一方、ガンバとしても、クラブが一枚岩になってクラブの難局を乗り切ろうと気持ちを揃え、13年を迎えた。
「今年1年でチームをJ1リーグに復帰させ、サポーターの皆さんに喜んでもらうということが大前提の目標ですが、スタジアム建設にも引き続き皆さんのお力を貸していただきたいと思っています。クラブとしてもチームとしても初めてJ2リーグを戦うシーズンで未知な部分も多く、大変な1年になるのは想像できます。ですがそういう時だからこそ、総力を上げて攻める、立ち向かうような、歴史に残るシーズンにしたい。皆さんにも、ぜひ『新スタジアム』を道標に、歴史に残る苦労をしていただきたいと思っています(野呂)」
新年、初出勤の日の朝礼で野呂が口にした決意に嘘はなく、この年、ガンバは従来から続けてきたホームタウン活動にも更に力を入れながら、通信インフラが整備されつつあった状況も利用して、SNSの有効活用、ホームページの充実、スカパー!での『ガンバファミリー』(スカパー!)の動画配信などを順次スタート。クラブの総力を上げて募金活動の追い風になるような新たな取り組みにも積極的に乗り出す。
その過程において、思わぬ事態に直面したのが、着工を目前に控えた13年2月だ。この頃にはすでに地盤の準備工事が始まっていたにもかかわらず、建設予定地である練習場の地下に、228メートルに及ぶ戦時中の弾薬庫であった空洞が発見される。結果的にその調査や申請、空洞部の埋戻工事などに多くの時間を要した。
当時、建築現場の総括作業所長として指揮を振るった中野達男と作業所長を務めた松尾享は「『3ない』工事」だったと振り返る。
「弾薬庫の調査と撤去に時間がかかったこともあって、本格的に工事がスタートした13年12月の時点で完成予定日までの工期は22ヶ月しかないという状況でした。本来、この規模のプロジェクトであれば最低でも28ヶ月はかかると考えても、かつてないスピード感を持って進めなければ到底、間に合いません。だからこそ、着工を待つまでの時間もとにかく無駄にできないと『いかに早く、いかに安く、だけど丁寧にいいスタジアムをつくる』ために、設計チームや建築チームでつくり込みの打ち合わせを着工までに100回以上繰り返しながら、綿密に準備を続けました(中野)」
「当時は、11年の東日本大震災の影響や21年に開催された東京オリンピック関連の準備が始まっていたことで、関西で現場を任せられる職方が大幅に不足していたんです。また資材も職方の労務費も高騰していました。という状況を鑑みて、現場には『お金がない、工期がない、人がいない』という『3ない』工事だとリマインドしていました。だからこそ、いかに少数精鋭で、なおかつ、その職方たちが最後までしっかり工事にあたれるチームワークが必須だと考えていました。当然、現場作業以外の工場製作に関わる人たちとも密に連携して寸分の無駄なく工事を進めなければいけないということも常に頭にありました(松尾)」
ただし、結果論ながら、ガンバのJ2リーグでの躍進が追い風となって、募金活動が活発化したのはポジティブだったという見方もできる。事実、このシーズンを通して募金額が伸びていったことは、先の設計チームの言葉を鑑みても『屋根付き、40,000人収容』のスタジアムがより現実味を帯びることにも繋がった。
また工事の具体的な話に移る前に、着工を待つ期間において、ホームゴール裏のサポーター席の見直しを図ったことにも触れておきたい。実はこの年、着工に先駆けて野呂はサポーターグループの代表者と新スタジアムに関する話し合いの場を設けている。その中で、サポーターから「ゴール裏が一枚岩になって戦えるようなつくりにしてほしい」と強く要望されたことを受け、ガンバサポーターが集うゴール裏席のみ、3層構造から2層構造への設計変更が決断される。言うまでもなく、この時期における設計変更は多方面に影響が出るのは承知の上で、だ。野呂をはじめ、設計チームの浜谷朋之、そして、新スタジアムの構造部門を担当した奥出久人が振り返る。
「新スタジアムは3層構造で、1層と3層の間にVIPルームが鉢巻のようにグルッと巻く形になっています。これは、建設にあたって海外の歴史あるスタジアムを視察したことがヒントになりました。というのも、海外のスタジアムにおいて、VIPルームは社交の場としても利用されることが多く、そこでさまざまな商談が行われたり、新たな事業を生み出しています。それを参考に、新スタジアムの未来を想像しながら、国内では最大規模となる2,000人を収容できるVIPルームを組み入れました。ただ、サポーターの皆さんからは『ゴール裏にVIPルームは必要ない。それよりもここに集まるサポーター、1万人くらいが一体感を持って応援できるような席にしてほしい』と。その意向を竹中さんにも伝え、様々な策を考えていただいた結果、最終的にはスタジアムの構造、工期、そして予算的にもギリギリどうにかなりそうな『2層』への変更に踏み切りました。それによって新たに10億円の予算が必要になりましたが、我々にとってサポーターの皆さんも大切な仲間です。また当初から謳っている通り、ここは『みんなの』スタジアムだからこそ、少しでもその思いに近づけたかった(野呂)」
「1層にすることもできないわけではないですが、そうなると全体の構造のバランスを図るために大幅な設計変更が必要になります。工期や予算を考えるとそれは到底、現実的ではありませんでした。ただ弊社としても、ガンバさんのご意向、サポーターの皆さんの想いに寄り添いたい中で、社内でも打ち合わせを重ねて絞り出したのが2層への構造変更でした。正直、他と断面が変わるというのは非常につくりにくいし、2層目のスタンドが柱位置より前に大きくはね出すことによる構造の不安定さも出てきます。ましてゴール裏サポーター席では、飛び跳ねて応援される方も多いですから。それをどうすれば解決できるかが、一番のポイントになりました。その過程では実際の試合でどのくらい揺れるのかを検証するため、埼スタのゴール裏に潜り込んで揺れを体感したこともあります(笑)。最終的には設計チーム、構造チームでも話し合いを重ね、最適解を導き出しました。机上の解析では問題ないと立証されていましたが、完成後に安全性を確かめるため、工事に関わった職方さんをはじめとする大勢の方にゴール裏で飛んでいただいて実証実験をしたのもいい思い出です(奥出)」
「スタジアムをコンパクトにつくるために、上下が積層する観客席の計画にしたのですが、現場に建ち上がるそれをピッチから見上げた時に巨大な『壁』に囲まれているような感覚になったんです。それはもう、図面からイメージしていた以上に…というと設計者として語弊があるかもしれませんが(笑)、正直、想像を超える『壁』感があった。まして、2層構造に変更したゴール裏がサポーターの皆さんで埋まる姿を想像すれば、これはもう、プレーする選手の皆さんはものすごい圧を受けるだろうなって思ったのを覚えています(浜谷)」
ようやく設計が固まり、かつ旧弾薬庫の対応も終わって着工に漕ぎ着けたのは、13年12月だ。先にも書いた通り、建築現場では、職方だけでなく、施工管理人員の不足も相まって、着工の日に現場に立った建築担当はなんと、中野、松尾を含めてわずか5人。建築規模の大きさから考えれば到底、あり得ない人数だ。そこからいかにして『完成』に辿り着いたのだろうか。
(文中敬称略)
―
高村美砂●取材・文 text by Takamura Misa

